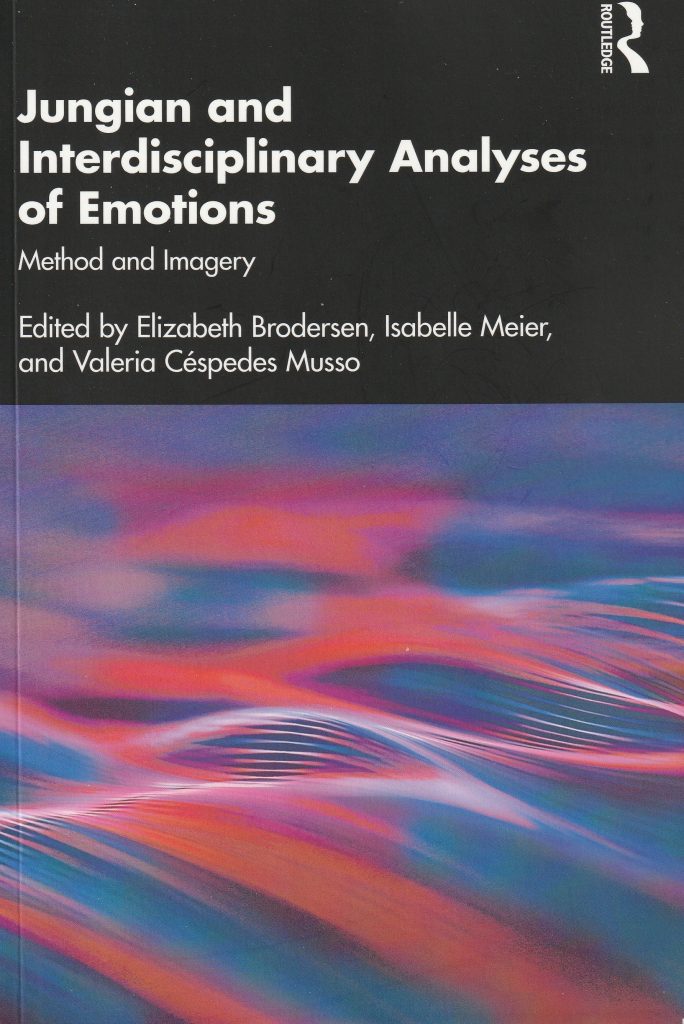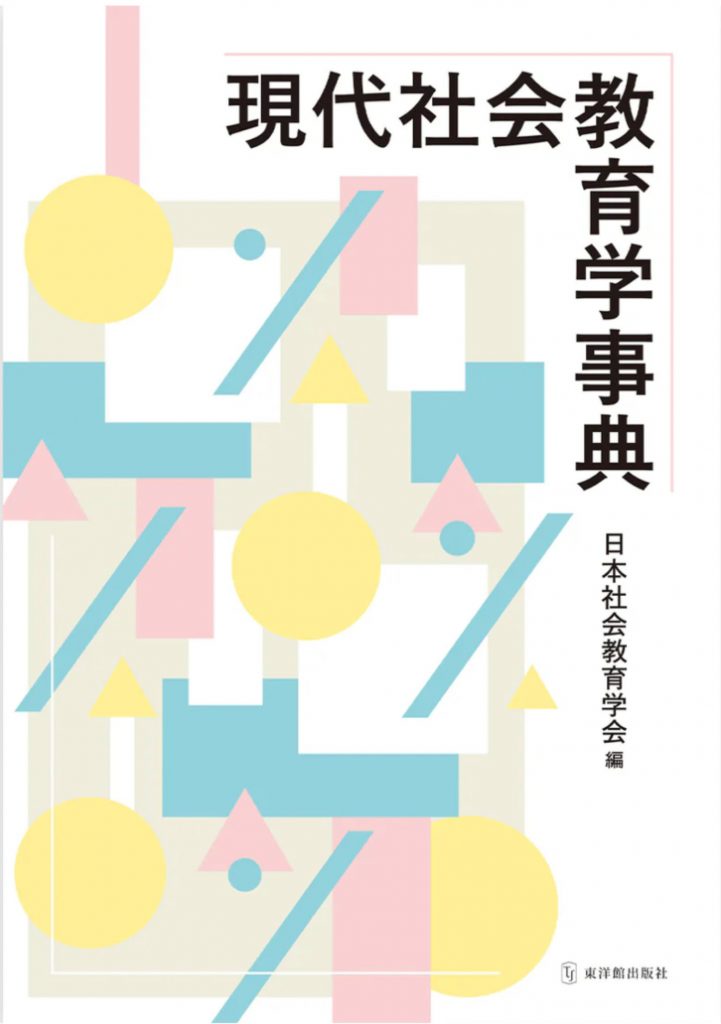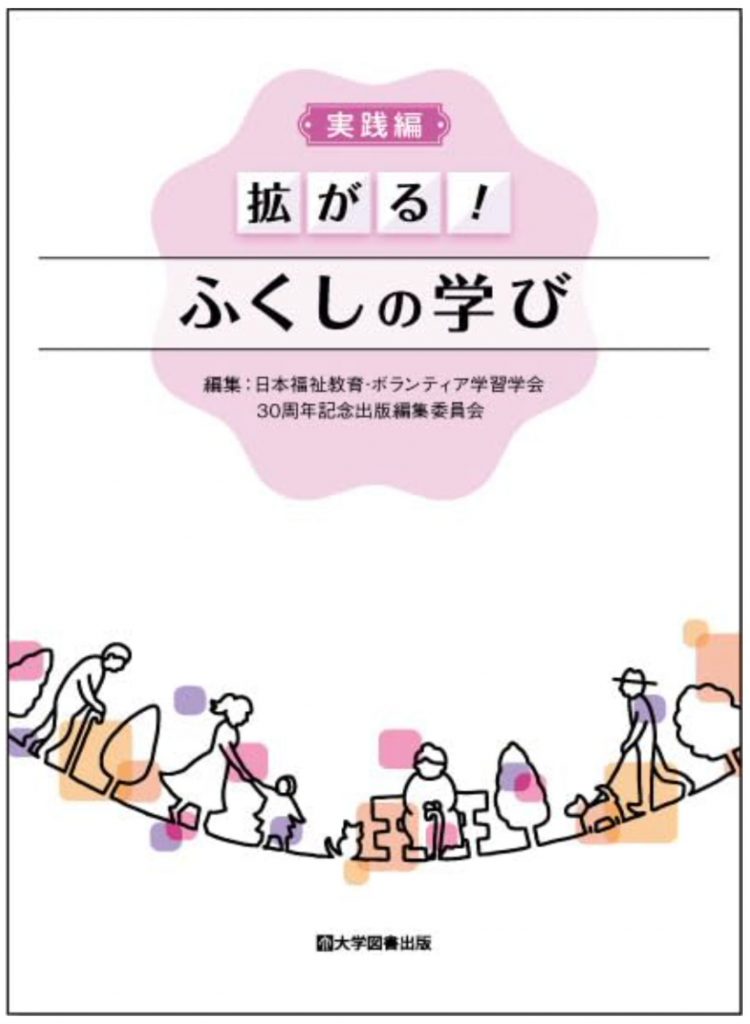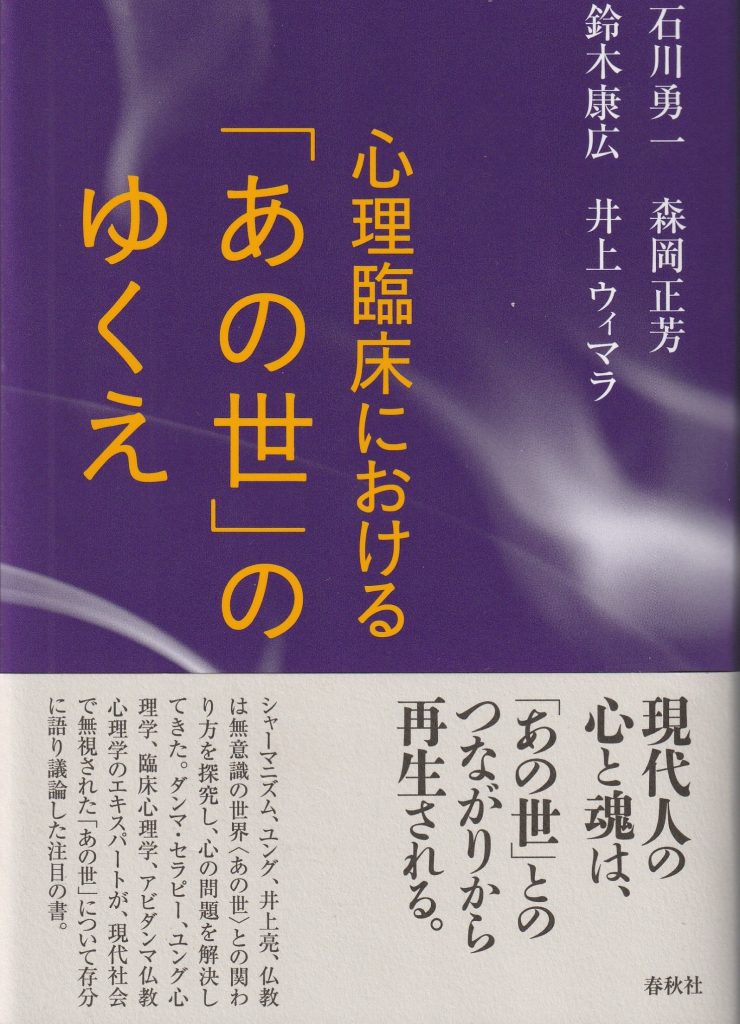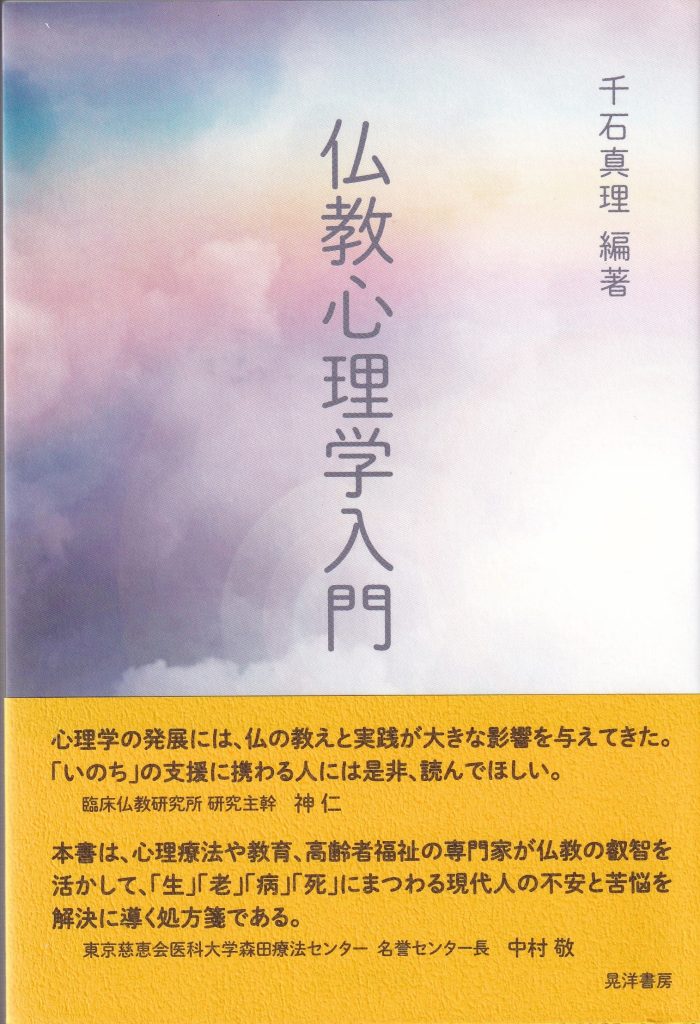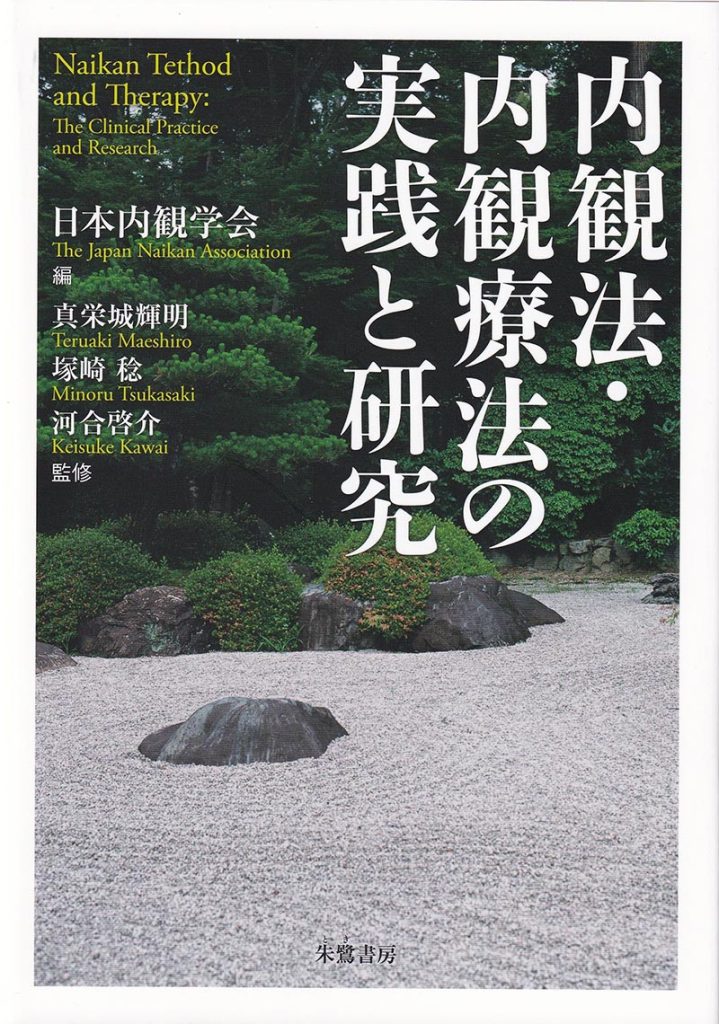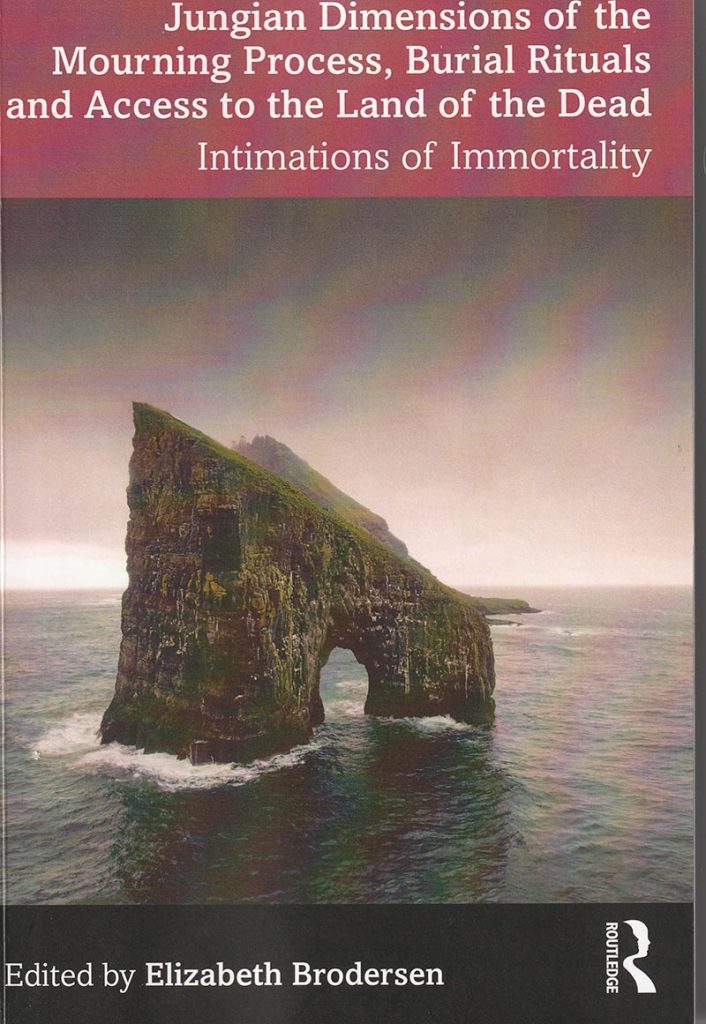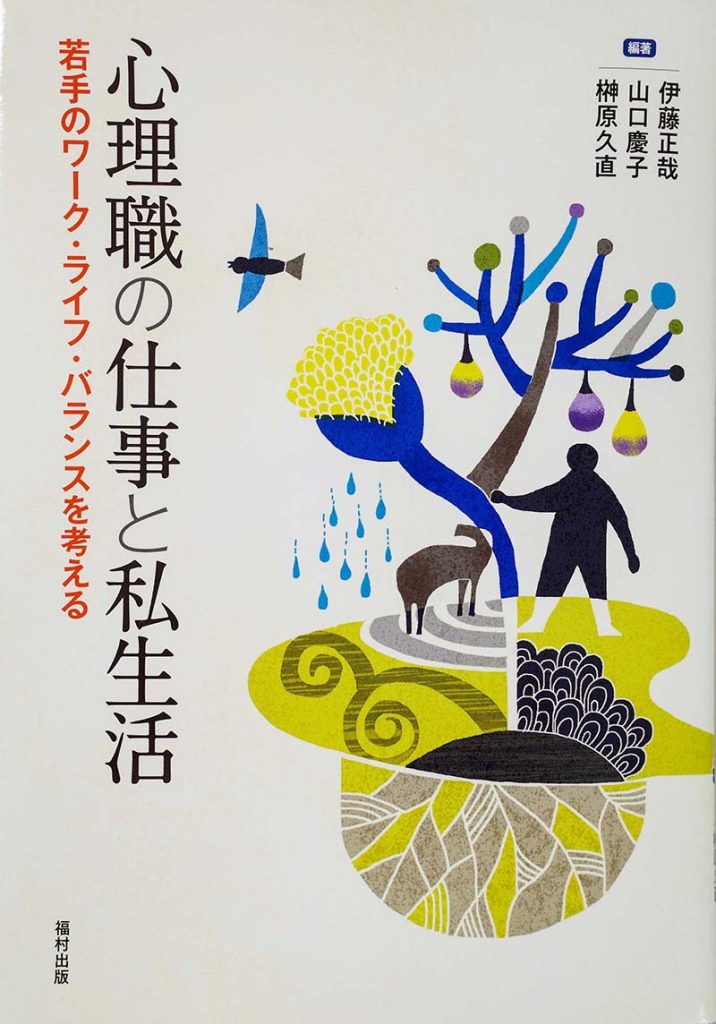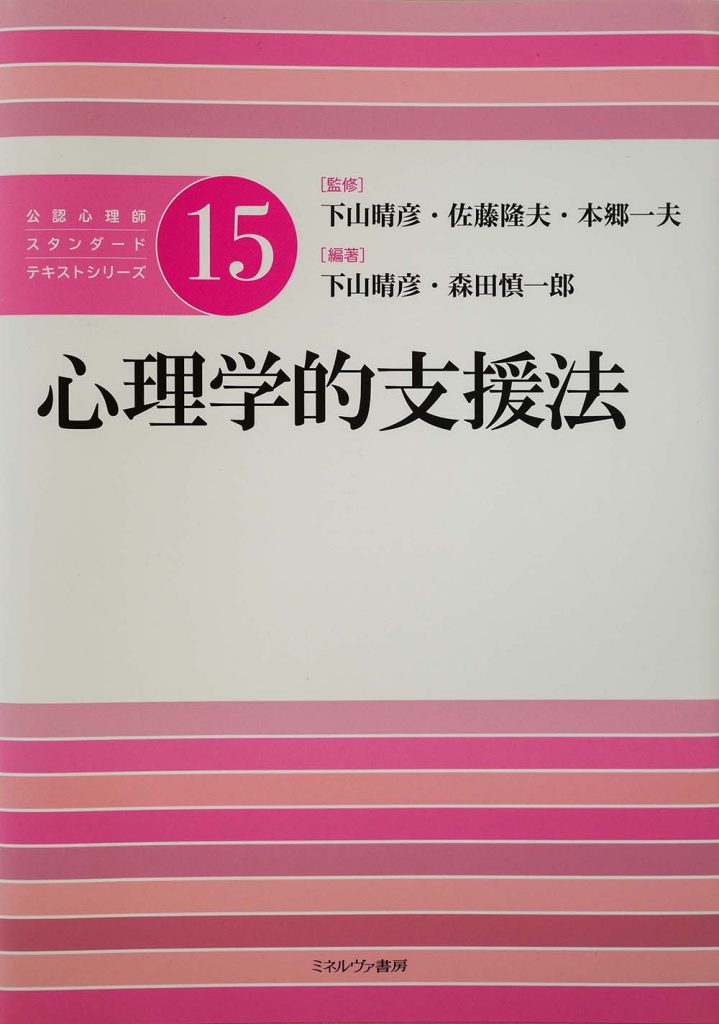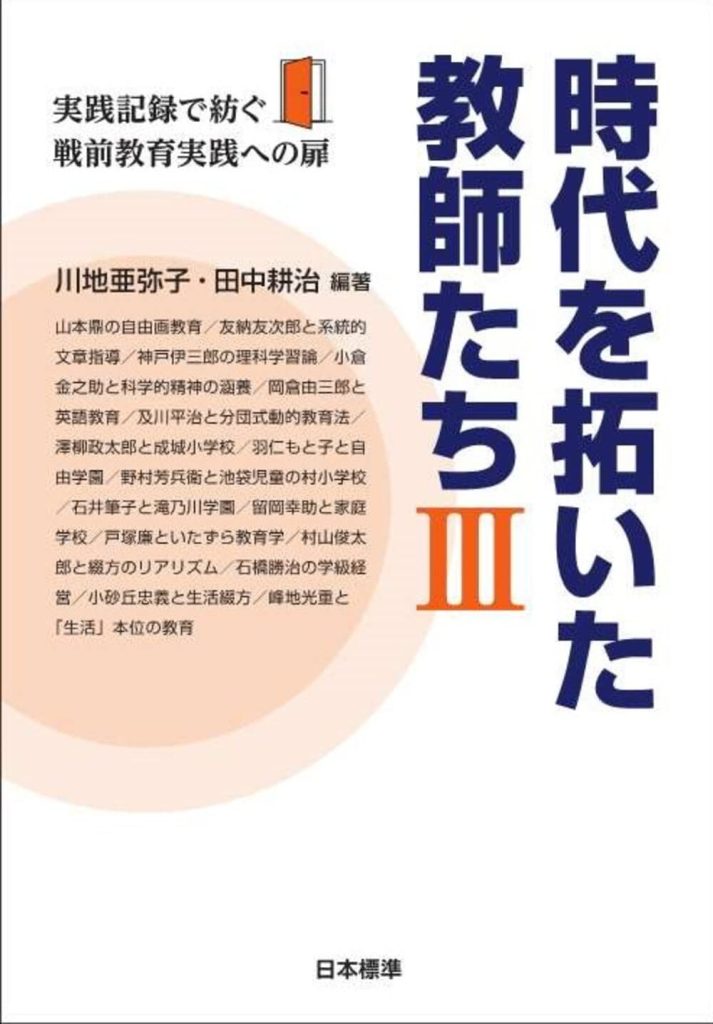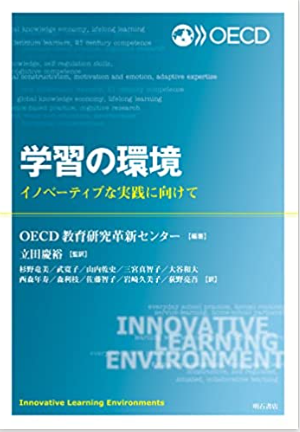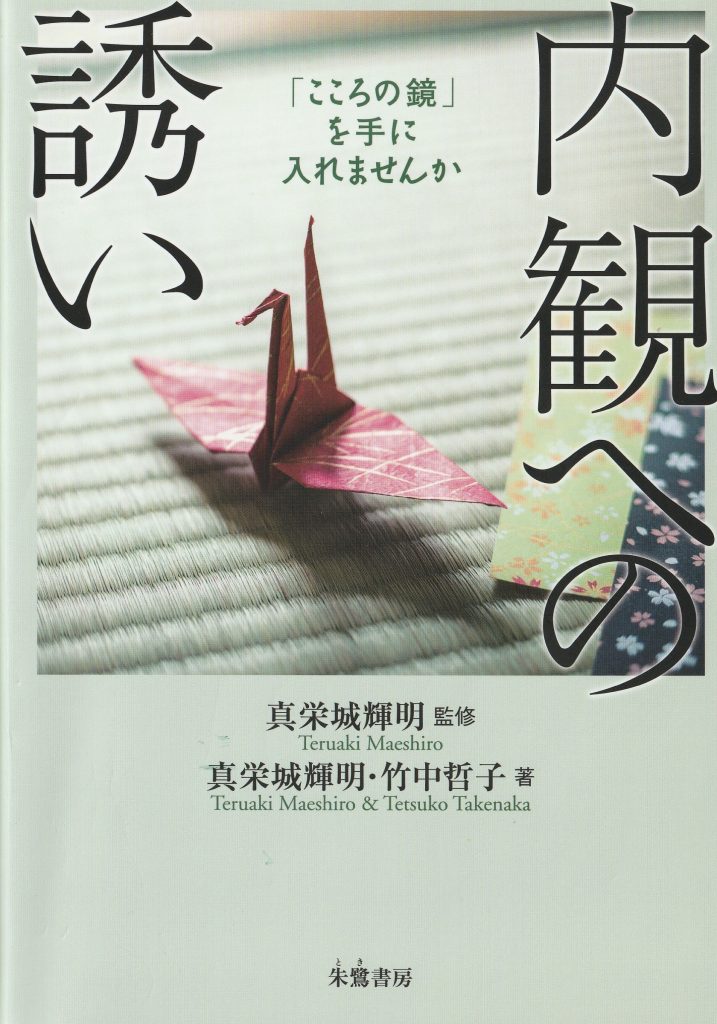Jungian and Interdisciplinary Analyses of Emotions: Method and Imagery
- Edited By Elizabeth Brodersen, Isabelle Meier, Valeria Céspedes Musso
- Routledge
- 2025.4
鈴木 康広先生(教育学部臨床心理学科)による紹介文
2023年7月にスイスの国際学会で”Emotion and Constellation from the Viewpoint of Buddhism”を発表した。仏教における「縁起の図」が、「脳」や「情動」といった複雑なシステムを「網の目のようなネットワーク」として理解する「見取り図」になることを論じた。また「自我境界」が「縁起の図」で拡充できることを追記して、東洋の仏教的観点が、西洋人の聴衆にインパクトを与えた手応えがあった。