批判的犯罪学: 刑事司法と犯罪研究を問い直す
- 批判的犯罪学研究会 編
- ちとせプレス
- 2025.9
山本 奈生先生(社会学部現代社会学科)による紹介文
批判的犯罪学という分野は、欧米では長年議論されてきたものの、日本ではほとんど知られてきませんでした。批判的犯罪学とは、現行の法体系における窃盗犯などよりも、大企業や国家が行う戦争や環境破壊のほうが問題だとし、既存の犯罪概念を批判するものです。この本は、日本ではじめて系統的にこの分野を論じた論文集です。編著の名義は特定個人ではなく、研究会となっています。皆でとても愉しく、コモンズとして作った本です。
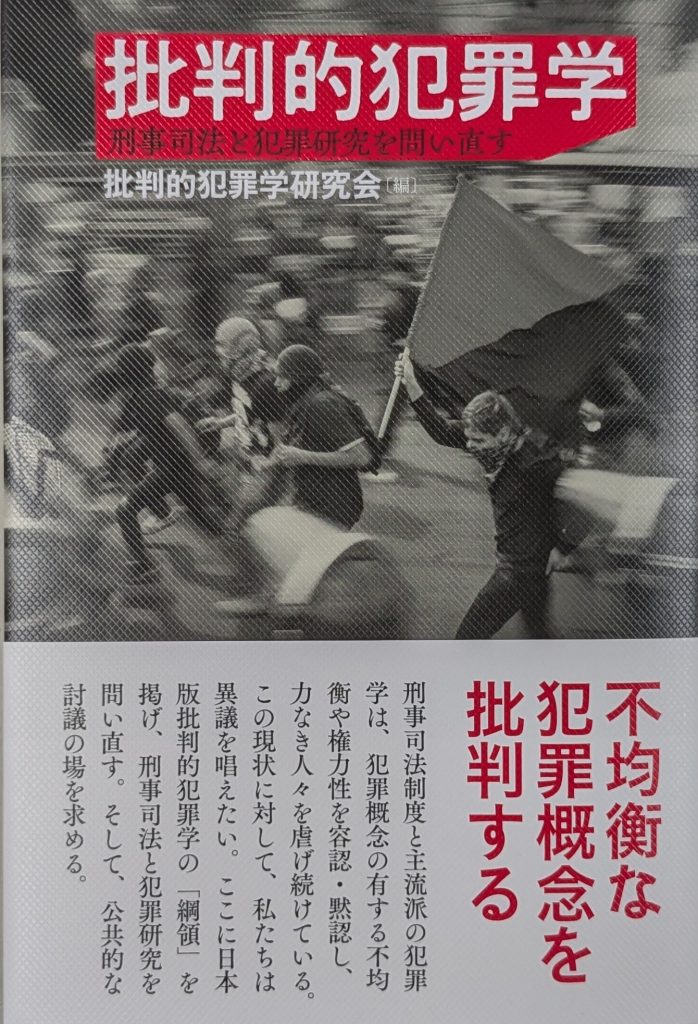
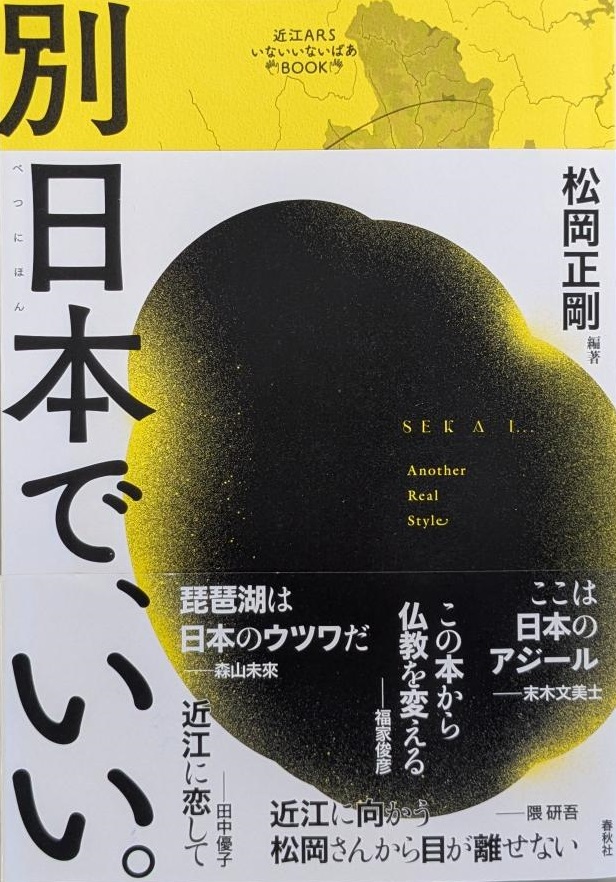
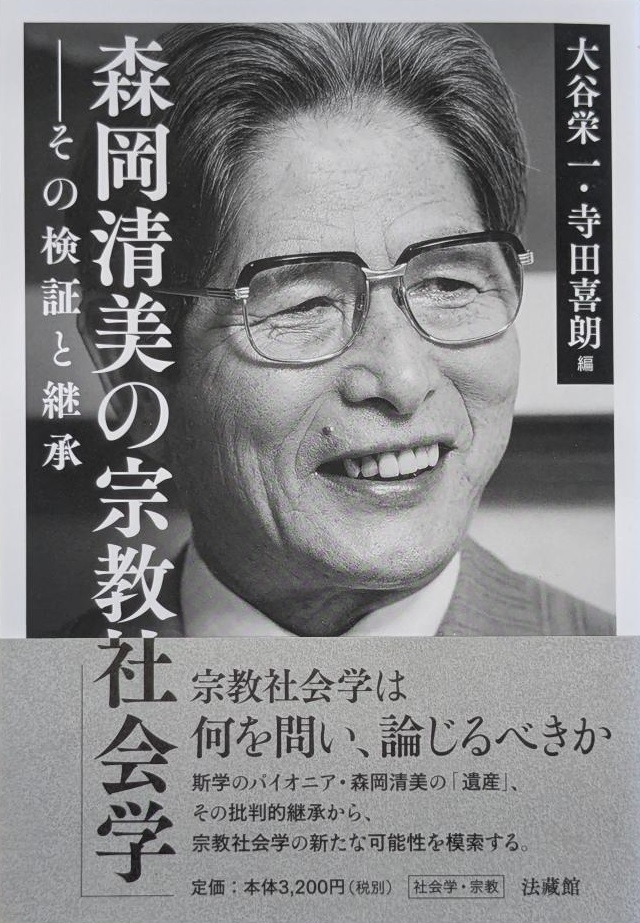
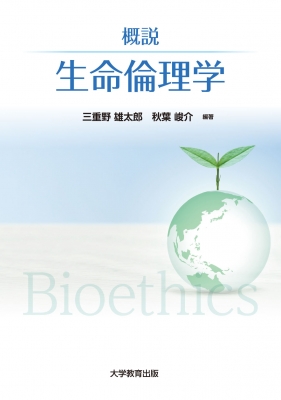
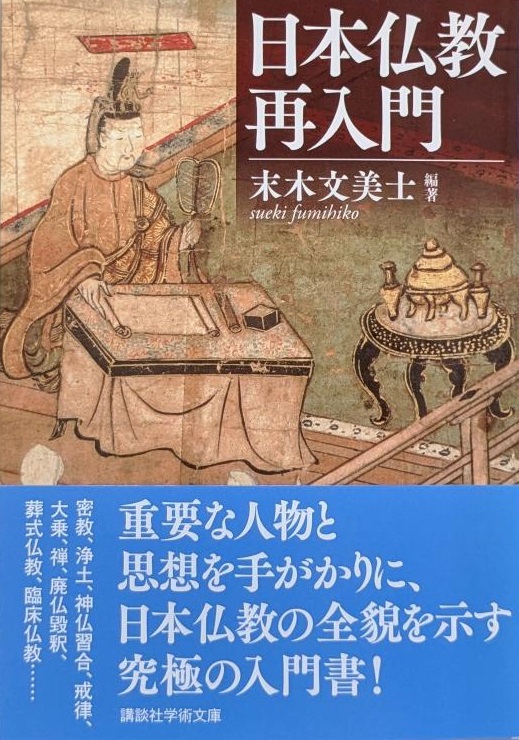
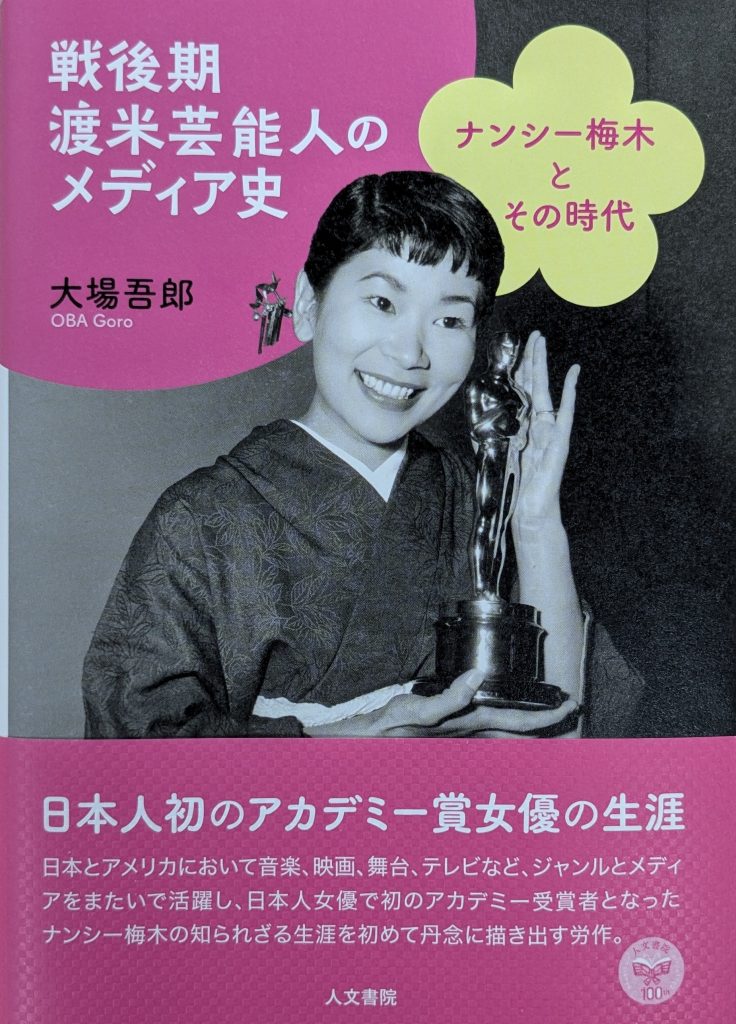
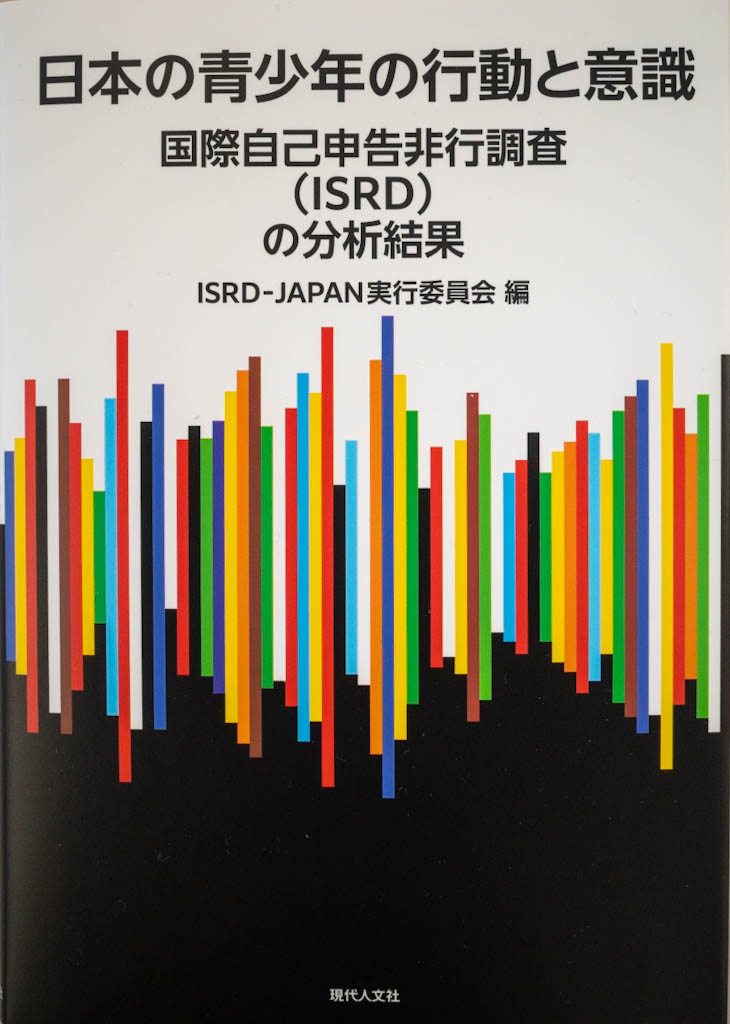
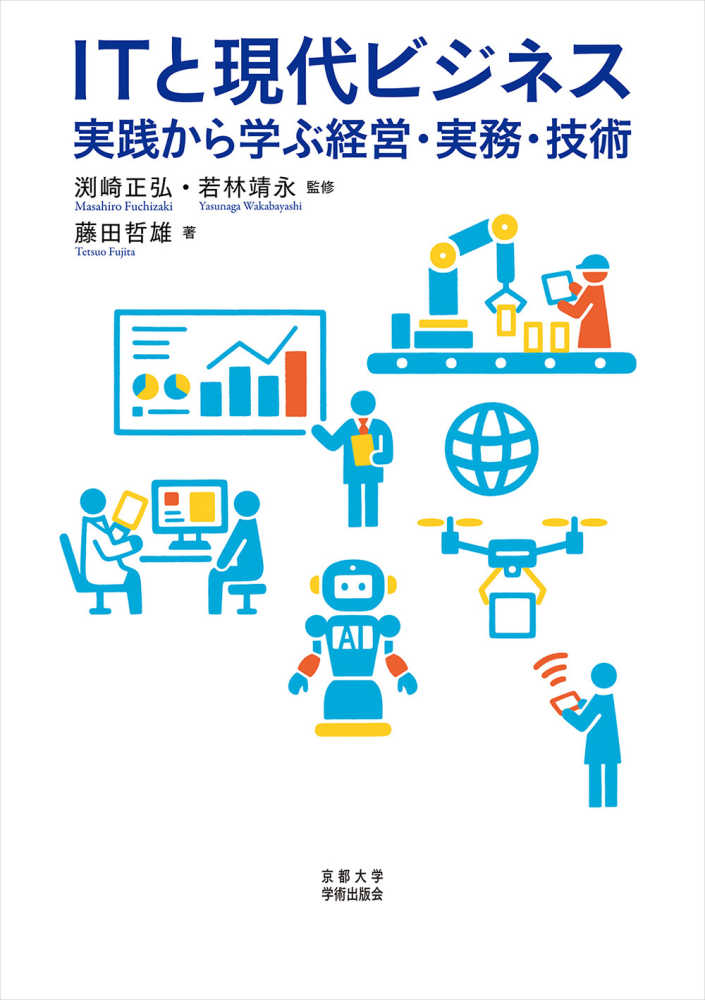
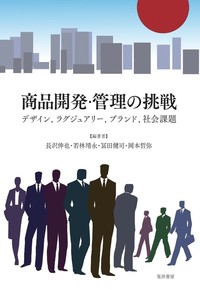
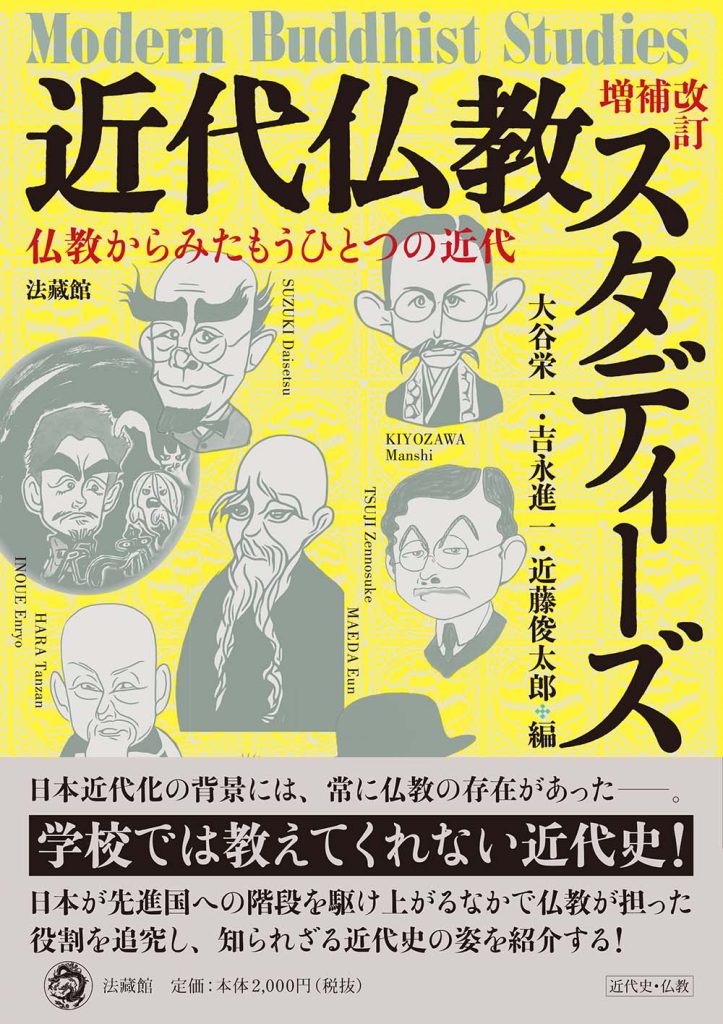
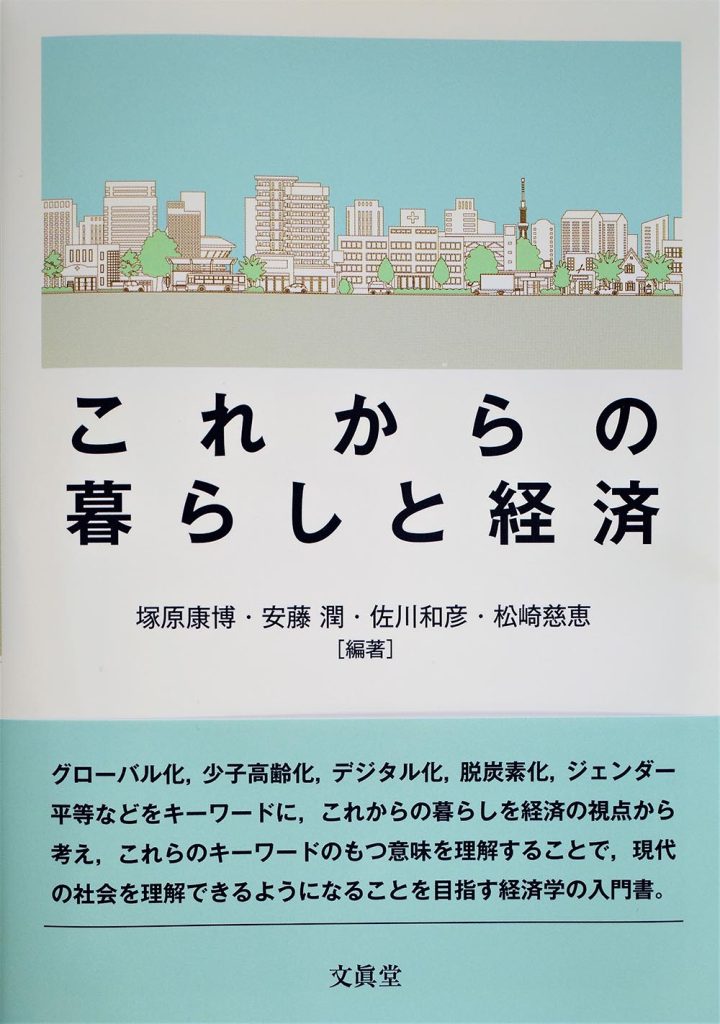
-716x1024.jpg)