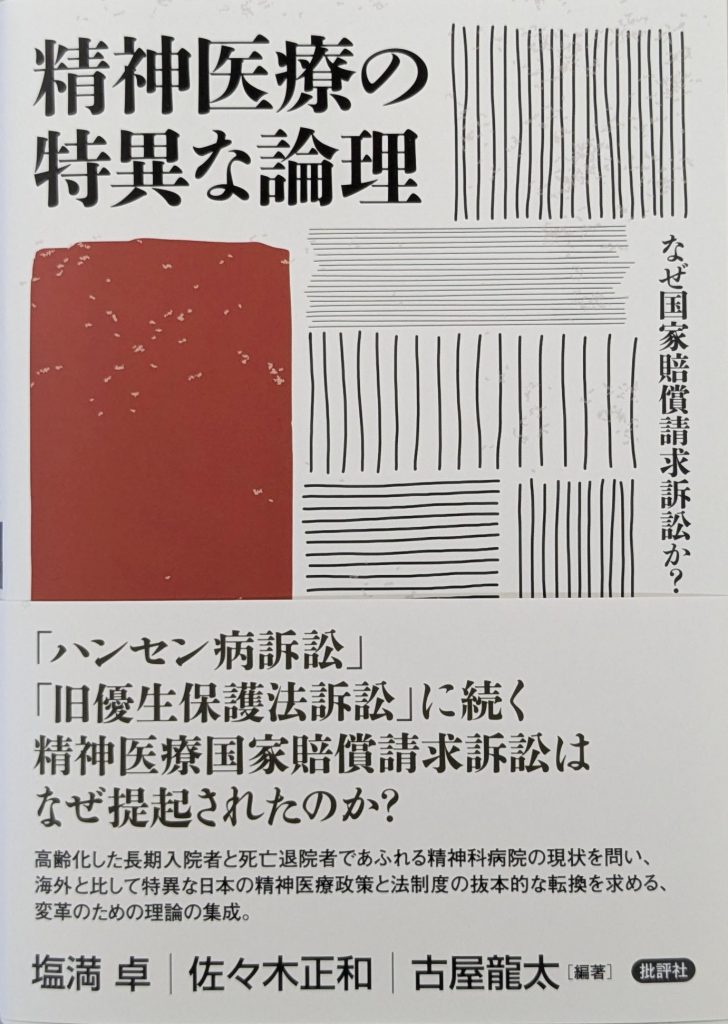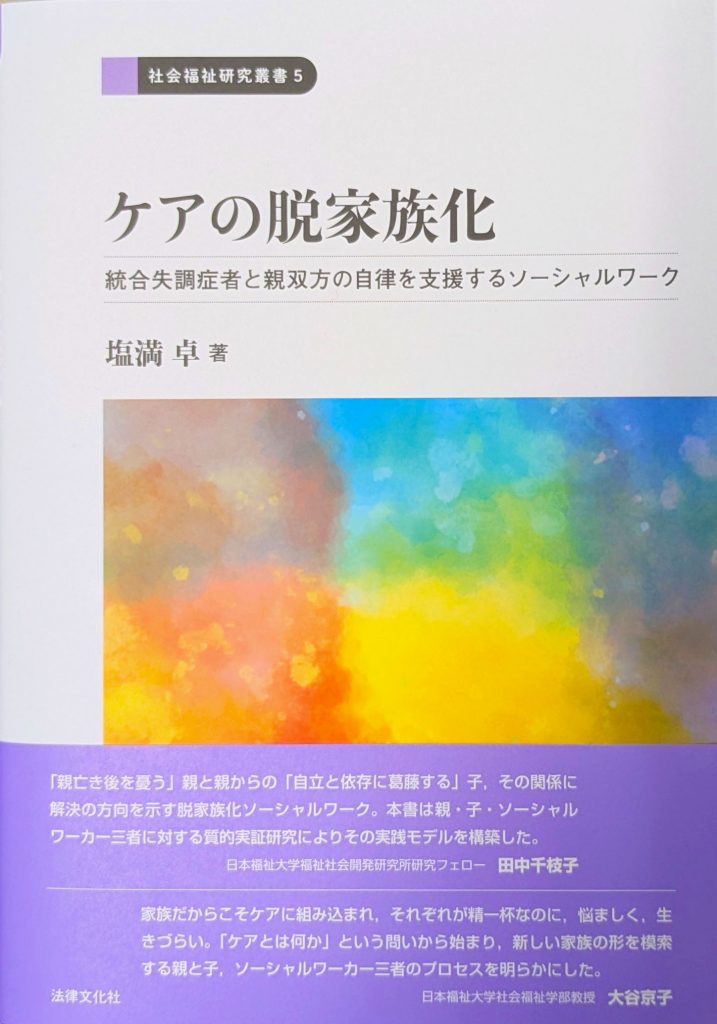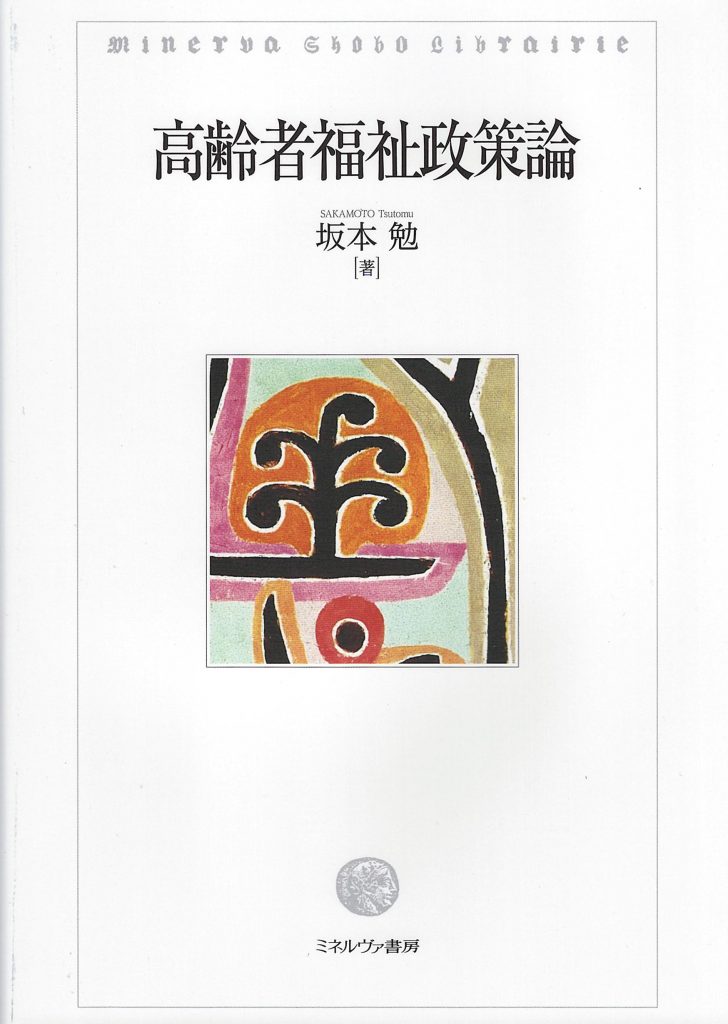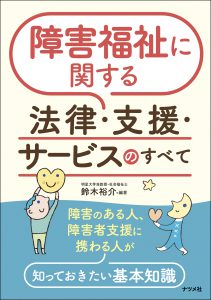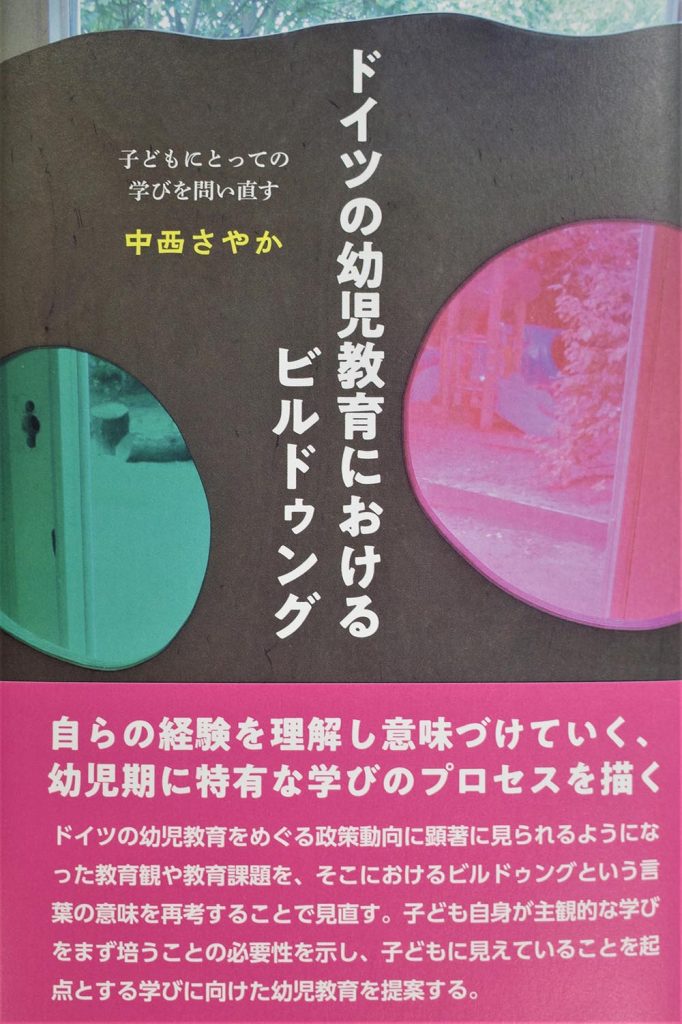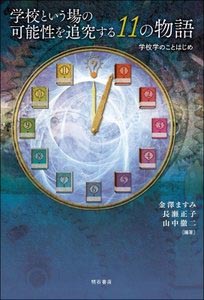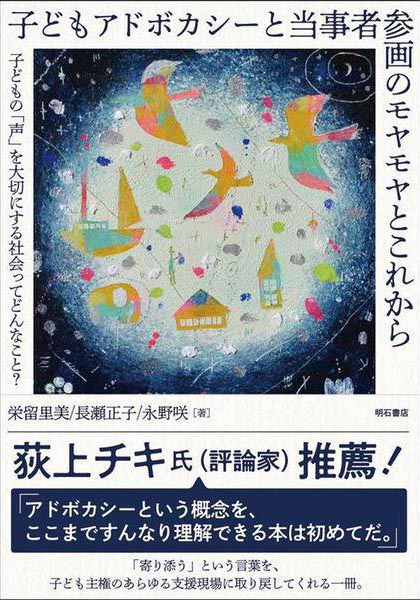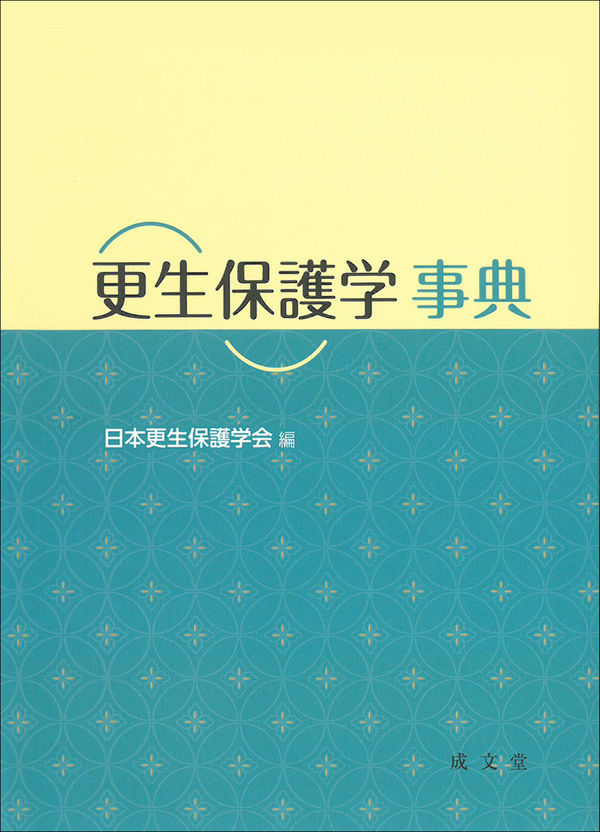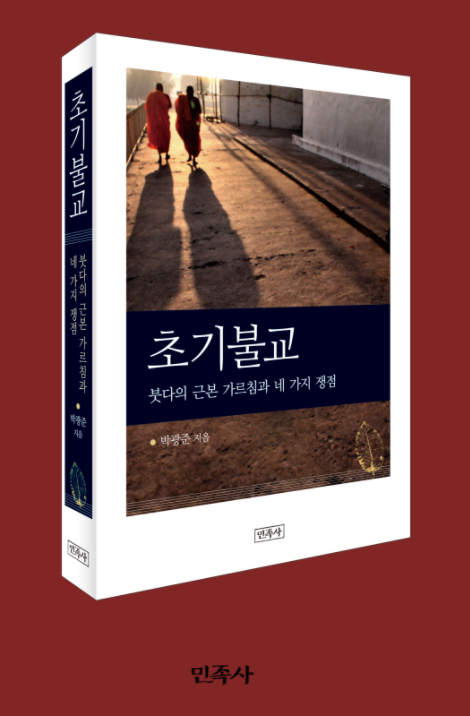精神医療の特異な論理 : なぜ国家賠償請求訴訟か?
- 塩満 卓、佐々木正和、古屋龍太[編著]
- 批評社
- 2025.12
塩満 卓先生(社会福祉学部社会福祉学科)による紹介文
なぜ日本は、精神科病院大国と呼ばれるようになっているのか。1997年に国家資格化された精神保健福祉士は、長期入院患者を削減する資格として期待され、精神保健福祉士法は成立した。しかしながら、資格化後、四半世紀を過ぎた現在においても、状況は変わっていない。本書は、歴史的制度的に精神保健福祉政策を批判的に論じ、人権擁護、ソーシャルインクージョン、エンパワメントといった社会福祉学で重要な概念が実践で生かされないわが国の精神医療制度の課題を多面的に論じた理論の集成である。